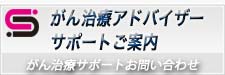がん治療は、多くの場合、外科医、内科医、放射線科医などの専門家が協力して行われる「チーム医療」が基本的なアプローチとなっています。
がん治療は、多くの場合、外科医、内科医、放射線科医などの専門家が協力して行われる「チーム医療」が基本的なアプローチとなっています。
しかし、一般的な病院では、医師がそれぞれの専門分野に分かれ、担当診療科医師が主治医となって治療を進めることが一般的です。治療方針の決定や進行管理は、その科に所属する医師たちが中心となって行われます。また、週に1回程度、カンファレンスが開かれ、患者の状況や治療方針などについて、複数の医師が協力して検討します。を集学的治療といいます。
また、がん診療連携拠点病院の指定要件には、患者さんの治療に携わる専門領域の医師、看護師などすべての医療関係者が参加する「キャンサーボード」の設置及び定期的な開催が含まれています。
キャンサーボードとは、患者さんの治療方針について、院内の専門家が集まって定期的に意見交換、共有、検討、確認を行う会議のことです。この会議には、手術、放射線療法、薬物療法などに関わる専門領域の医師や看護師が参加します。
キャンサーボードは、治療方針を決定する際に、多数の医療関係者の意見を総合的に考慮することができるため、より適切な治療方針を提供することができます。また、治療方針に関する情報共有や意見交換により、医療関係者の知識や技術の向上にもつながります。療スタッフなどで意見交換され診療科の垣根を越えて治療方針が決定されます。
がん診療連携拠点病院は、キャンサーボードの設置及び定期的な開催を通じて、患者さんに最適な治療を提供するために取り組んでいます。

【目次】
がん治療の現状 手術(外科治療)
がん治療 手術で治癒をめざす
拡大手術から縮小手術になってきましたが
ひとすじに手術映像を究める!
固形がんの治療は「局所治療」と「全身治療」に大きく分けられます。
がんが発生した原発巣とその近傍の少数の転移であれば、手術や放射線などの局所治療で“治癒”が期待できます。
管腔臓器(胃、十二指腸、小腸、大腸など)の場合、腫瘍細胞が上皮内にとどまっている状態は「上皮内新生物・良性腫瘍」といいます。実質臓器(肝臓、腎臓、膵臓など)の臓器にでは血管やリンパ管がある部分まで浸潤しない腫瘍です。基本的には転移することはほとんどありません。がん「悪性新生物・悪性腫瘍」は粘膜の上皮の下の基底膜を破って無秩序に増殖し、浸潤(しんじゅん)します。「浸潤」がん組織が周囲に染み出るように広がっていくこと。
多くの場合各臓器の癌取扱い規約(ガイドライン)に沿って、治療法の選択や治療効果を評価します。同じ臓器のがんでも細胞レベルでは多種多様であり、その種類が治療法の選択にも影響するので、病理医が、顕微鏡などでどんな性質の癌なのかを組織や細胞の形などから組織分類します。がんの進行度を病期(ステージ0~Ⅳ)に分類します。
「TNM分類」術前・術後にがん巣の大きさ、リンパ節への転移の有無、他の臓器への転移に分類します。
治療は「癌取扱い規約」に従うことで、共通の尺度での診断や治療が可能となるわけです。各臓器別の専門学会で数年毎にに見直しされて改正されます。 また、最近では遺伝子情報(がんゲノム医療)に基づくがんの「個別化治療」も行われています。遺伝子変異などのがんの特徴に合わせて個々にに適した「個別化治療」を行うことができるようになってきました。
画像診断、術前の細胞診、組織診などで、がん巣(がん細胞の組織の塊)が原発部位に留まっていると診断がついたなら、がん治療の根治的治療は手術です。 根治性を高めつつ、術後のQOL(生活の質)を考慮して機能を温存する低侵襲(ていしんしゅう)手術の鏡視下手術も普通になってきました。耳鼻咽喉科の分野では内視鏡下手術も増えています。鏡視下手術(胸腔鏡、腹腔鏡を胸、お腹の中にいれ、モニターを見ながら手術を行います)や、ロボットアームを操作するロボット手術の代名詞になっている「da Vinci」(ダビンチサージカルシステム)もさらに進化しました。その推移は毎年増えています。
手術器具を動かせる範囲に制限があるため難易度が高いことと、通常の手術より時間がかかる傾向がありますが、高解像度のモニターで、手術に参加している医師全員に詳細に手術の手技がわかります。通常の手術より傷が小さい、術後の痛みが少ない、など体にかかる負担が少ないので術後の回復が早いです。
さらにダヴィンチを用いた手術支援の「ロボット手術」では、鏡下手術手術では難しいとされていた動き、視野が可能となり、さらに手術成績の向上が期待されます。
がん治療 手術で治癒をめざす
 限られた部位の治療を「局所療法」といいます。初期治療の目的は、“治癒”をめざすことです。局所療法は手術(外科療法)と放射線療法があります。 手術は局所がんをどのように切除、摘出するかが主眼におかれています。
限られた部位の治療を「局所療法」といいます。初期治療の目的は、“治癒”をめざすことです。局所療法は手術(外科療法)と放射線療法があります。 手術は局所がんをどのように切除、摘出するかが主眼におかれています。
さらに、より高い治療効果を目指して、手術や薬物療法、放射線治療などの治療法を組み合わせて集学的治療行います。
腹腔鏡下手術など低侵襲で行える手術術式が増えてきたことは朗報です。 腹腔鏡下手術が一般的になる前は、 腹腔鏡下手術は一部の施設でしか行われていませんでした。当時(25年くらい前)の学会での発表でも、30代くらいの若い医者が発表するときは、結語は「有用と思われる」と結んでいました。「有用である!」と私が勧めてもなかなか、その言葉は使えませんでした。昔ながらの医学会の雰囲気もありました。学会での重要なようなポジションを占めている教授は50歳以上です。当時はモニターを見ながら、手で臓器を触ることができない手術を後押しすることなど考えられなかったと思います。
それが今は、デバイス(使用する器具)等の発展、手技の工夫もあり現代は普通になってきました。腹腔鏡下手術で使用するデバイスは、国産は非常に少なくアメリカ製がほとんどです。そのころの外資系の会社からの手術映像の制作は多く、メジャーな学会でブランド病院の医者が学会のシンポジウムでの発表は評判がよかったです。技術を習得するのに経験を要しますが今や腹腔鏡下手術ができない基幹病院はありません。
ダヴィンチを用いた「ロボット支援手術」も行われています。当初は泌尿器科で行う再建手術(前立腺摘出後の尿管の吻合は明確に利益「ベネフィット」があります)から始りいまや消化器外科、婦人科などの手術にも用いられています。しかし、全ての症例に適応になるのではなく、腹腔鏡下手・ロボット支援手術の対象ではありません。
高度の熟練度のこともありますが従来の術式の方が優れている場合もあります。手術は、根治性、安全性、低侵襲性(機能温存)に考慮して行われます。 低侵襲性はもちろん重要ですが、がんの手術は、まず、がん巣を確実に切除、摘出できる根治性が最優先されるべきで、 がん巣を安全に確実に取り切れることを重視します。そのとき低侵襲性を考慮することになります。
固形がんの場合、第1選択は手術です。がん巣が局所にしか存在しなければ切除、摘出できれば確実に治る可能性が高いからです。麻酔学の発展により安全に手術することができ、またQOLを考慮した再建法の術式も進んできました。
一方、症例にもよりますが、手術は成功したのに再発する場合もあります。CTなどの画像上でがん巣が見えなくなっても、微小ながん細胞が残っていた可能性もあります。手術は、検査で確認されているがん巣を含んだ臓器の切除、摘出と所属リンパ節、周囲のリンパ節の郭清です。
隣接する臓器にがんの微少転移があるかどうか、術中迅速病理診断、術後の病理診断をします。切除断端が陰性(Cancer negative)、洗浄細胞診が陰性でも数年後に再発しないとはいえないのです。それは難易度の高い手術が成功しても、検査では、存在を確認することができないほど微少な遠隔転移があったとたと考えざるを得ないです。実際の手術症例では、外科の医者は何度も経験しています。
そのため術後、化学療法、放射線療法などの補助療法としておこなうこともあります。患者さんの年齢、体力、臓器の温存など種々の要因で、放射線療法を選択したほうがよいこともあります。放射線療法の技術も格段に進歩を遂げており、手術と同等の効果が期待できる場合もあります。ただし臓器によって放射線に対する感受性が異なりますので、原発巣がどこのがんかによって違います。
手術でがん巣を完全に摘出できる場合、根治的手術の適応になります。「がんの根治性」「臓器の機能温存」「治療の安全性」の要素から判断します。手術を受けると、なにかを犠牲にしなければならない場合も出てきます。患者さんも、主治医にどんな手術でどんな後遺症が残るのかを質問して、自分の意見を伝えることも必要だと思っています。
手術手技も拡大手術から腹腔鏡手術を始めとした縮小手術に向かっています。手術で用いる新しい器機の登場により手術時間も短くなり術後の合併症も少なくなりました。麻酔学の発展も寄与していることも忘れてはいけませんが。自覚症状がなくても検診などで1センチ以下のがんでも、発見されたら手術が第1選択になります。内視鏡手術の適応になる場合もあります。しかし、固形がんでは病理検査でがんと確定診断された場合経過観察にはなりません。
早期と言われているがんでも、手術して病変を切除して、検体の病理検査で切除断端も陰性また所属リンパ節にもがんの転移がなくても、数年後に再発する場合があります「がん幹細胞」の存在があるからです。がんが発見されたとき転移するのかしないのか、あるいは手術したことによってすでに転移している微小ながんが増大するのか今の医学ではわかりません。
がんは転移がなければ恐い病気ではないのですが、日本人の平均寿命が伸びているとはいえ、結果的にがんは1981年以降ずっと日本人の死因第1位で、生涯に約2人に1人ががんと診断されています。
拡大手術から縮小手術になってきましたが
拡大手術から縮小(低侵襲)手術に移行することで、患者さんにとって多くの利点があります。まず、手術の傷跡が小さく、痛みが少なく、術後の回復が早いことが挙げられます。
また、出血量が少なく、手術後の合併症の発生率が低いという利点もあります。内視鏡や鏡視下手術、ロボット支援手術などの手技は、患者さんにとっては安全で確実な手術が可能になると同時に、医師にとっては精密な手術ができるため、手術の成功率も高くなるというメリットがあります。
しかしながら、これらの手術にはいくつかの欠点もあります。例えば、手術に必要な機材や器具が高価であるため、費用がかかることがあります。また、手術に必要なスキルや経験が高度であるため、手術が行える病院や医師が限られていることもあります。
総じて、拡大手術から縮小(低侵襲)手術に移行することで、患者さんにとっては多くのメリットがありますが、医師にとっては高いスキルや経験が必要です。
20年位前まではがんを確実に切除するために周囲を大きく切除する拡大手術がが主流でした。
しかし、大きく広がっている場合は、たとえ切除、摘出が可能でもがんは既に全身病になっている場合が多く、術後のQOLが著しく低下することもあります。
今はほとんどの医療機関でがんが進行していない場合は、機能温存のための縮小手術がおこなわれつつあります。たとえば乳がんで<あれば20年位前は全摘した症例がほとんどでしたが、腫瘍の大きさや進行度などを考慮して今は温存手術が主流になっています。それでも術前の抗がん剤治療と放射線治療も行う場合もあります。また術後も抗がん剤、放射線さらにホルモン療法を行うこともあります。それでも数年後に再発(局部再発・遠隔転移)される方もいます。
乳がんは5年後も再発する可能性は高いので、抗がん剤、ホルモン療法の継続的投与(5年〜10年)を続けますが、再発する理由を論理的に言い切れる医者はいません。また乳房温存手術では術後、放射線治療が標準治療になっています。 それでも2021年日本放射線腫瘍学会が行なったインターネットでの調査(乳がんと診断された1年以上5年未満の患者さん309人)では、乳房温存手術を受けた患者さんの 13・2%に当たる21人の方は手術後に放射線治療を受けていませんでした。6・5%の10人は放射線治療が必要なことさえ知らされていませんでした。
日本では年間15万人超が大腸がんと診断され、20%近くの人が肺や肝臓など他の臓器に転移したステージ4です。 従来は転移した部位の切除できない場合でも、原発巣の切除が可能な場合、治療の有用性は不明でも手術を行うこともありました。 切除後に抗がん剤を投与した群と、切除しなかった群と、ほとんど生存期間が変わらなかったとの結論を、 国立がん研究センター大腸外科が中心となって2021年4月に日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)がまとめました。 今後、大腸がん治療ガイドライン訂正につながる可能性もあります。
胃がんであれば切除あるいは胃全摘した場合、リンパ節の郭清範囲が20年位前は臓器の所属リンパ節の2群(D2)あるいは3群(D3)までの拡大手術が行われていました。スキルス胃がんも術前に抗がん剤の投与(ネオアジュバント療法)を行ってから手術をします。術後も継続的に抗がん剤の服用もありますが、それでも再発します。 逆に抗がん剤の服用をしていない方で5年以上経過しても再発しない方もいます。 抗がん剤の服用していた方のほうが再発率が数%違うだけです。抗がん剤の服用ですから長期に渡った場合副作用が出ます。
必ずしも高侵襲手術(拡大手術)は利益がないわけではありません。拡大手術が必要とされる症例もあります。「拡大手術」から「縮小手術」になってきた背景には手術で用いる医療機器の進歩もありますが、拡大手術でも縮小手術でも手術後の治療成績は変わらないということが実証されたからです。また最近は薬物療法が進歩してきましたので体への負担を考えて、がんとの共存を目指す薬物療法を選択する場合もあり、その方が患者さんの利益になることもあります。
コントロール臨床試験(従来の標準療法との比較試験として行われることが多く正確性が実証できる)で調査した結果、乳がんの手術も手術前の薬物療法を行って拡大手術から乳房を温存する縮小手術に変わってきています。日本人に多い肺がん・胃がん・大腸がんなども縮小手術になってきました。
腹腔鏡下手術や、より正確な手技を可能にした手術支援ロボット『ダヴィンチ』などが登場しました。しかし腹腔鏡による肝臓切除手術で死亡事故が多発した ケースもありリスクもあります。肝臓・膵臓など実質臓器の切除など、腹腔鏡手術では難しいケースもあります。例えば、ほとんどの場合最近まで子宮頸がんでは従来「準広範・広範子宮全摘手術」の開腹手術が行われてきました。
それでは、新しい腹腔鏡手術・ロボット支援手術の方が術後の治療成績がよいかというと、そんなことはありません。再発せずに治癒している割合は従来の開腹手術の術式と変わりません。子宮頸がんに罹患される方も多いのですが、腹腔鏡手術・ロボット支援手術では、熟練度の要素など考慮する必要もあります。手術においては根治性が保たれることが前提になるからです。
ただ新しいからとかで決めずに主治医と納得する話をしてください。その上で神経も極力温存する骨盤神経温存術式が可能か相談してください。
部位にもよりますが、腹腔鏡下手術や胸腔鏡下手術の適応になったとしても傷が小さい、入院日数が短いなどの理由だけで選択してほしくないと思います。進行したがんに対しては、高い技術力が必要な手術もあるからです。個々の患者さんの状態を鑑みて納得する選択をするための話し合いが大切です。
時代の流れからロボット支援手術を取り入れていない外科病院は、今後たちゆかなくなる可能性もありますが、医師の趣味に付き合う必要はありません。
ひとすじに手術映像を究める!これが私のモットーです
私は、長年に渡りがん治療の最前線で各領域の医学学会での手術症例の制作に携わってきました。 2,000症例を超える経験からの言葉です。
癌研究会付属病院(現がん研有明病院)などの専門病院、大学病院での多数の実績があります。 中川 健先生(元がん研有明病院院長・現名誉院長)の監修のもと一般向け「がん、治癒への闘い Vol.1 肺癌編 」など多数あります。 がん、治癒への闘い Vol.2 胃癌編 「癌研究会付属病院外科高橋 孝先生監修」、治癒への闘い Vol.3 大腸癌編 「癌研究会付属病院外科高橋 孝先生監修」
東京大学医学部付属病院、がん研有明病院はじめ専門領域の学会からの制作があります。教育用の「手術手技シリーズ」も領域別に多数の制作があります。その過程で多くの各領域の医師と出会い、個人的にも医師の本音での話も聞き、多くの医学学会に参加してがんについての知見を多く得る事ができました。
頼れるがん治療アドバイザーを目指します
しかし、がんの告知を受けた患者さんは精神的にもかなり深刻な状態です。 冷静な判断力を失っている場合も多いと思います。丁寧な説明を受けても、それを理解するまでには時間がかかります。
患者さん自身が治療に関して理解を深め、納得した上で選択した治療を進めることができるよういつでもサポートできるアドバイザーになりたいと思っております。悔いの無い治療を心より願っております。
がんの治療は、医師と患者さんとご家族の方の密接な連携が何より大切です。インフォームド・コンセント((納得と治療の選択)の普及の一助となれば大変意義深いことと考えております。
がん治療の現状 手術(外科療法)
がん治療の現状 薬物療法(抗がん剤)
がん治療の現状 放射線療法
がん治療の現状 がん治療の難しい理由
がん治療サポート内容 最善のがん治療を受けるために
「がん治療相談」がん治療アドバイザーによるサポート
オピニオン(がん治癒への道)
がん標準治療を選択するとき
「がん標準治療」生存率
がん先進医療(精密医療)
がん免疫療法
がん発生メカニズム
がん再発・転移
がん幹細胞
がん悪液質(あくえきしつ)
がん遺伝子治療
標準治療以上に自由診療の治療成績がよいということではありません
新型コロナウイルの基本知識